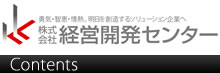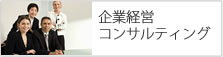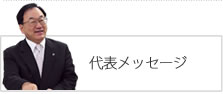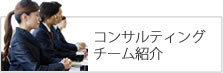|
平成25年がスタートし早いもので1ヶ月が過ぎました。皆さまの中には年初に今年の“目標”を立てられた方も多いと思います。また4月より新年度がスタートすることもあり、これから“目標”を立てられる方もいらっしゃると思います。 この度は、そんな目標設定についてレポートさせて頂きます。 一言で“目標”と言いましても、リーダーの皆さまは『法人・施設・部門の目標』・『自分の目標』・『部下の目標』と扱う“目標”はさまざまです。それを整理するためにも、それぞれのステップに分けて確認していきます。
ステップ①:必要性の検討 下表を参考にその目標がどこの領域に分布するかを確認し、目標として取組む必要があるかを検討します。
A領域 この領域は重要度も緊急度も高いため、目標として扱わなくても取組むことが多いです。ただ、この領域の業務に追われて他に何も取組めないという現状もあるのではないでしょうか? B領域 この領域は緊急度が高いために、どうしても取組む必要がありますが、重要度が低いために“誰が”取組む必要があるかを検討する必要があります。 C領域 A・B領域は緊急度が高いため取組まざるを得ない領域ですがこの領域は重要な領域にも関わらず、緊急度が低いためになかなか手をつけない領域です。ただ、この領域は将来的にA領域へとスライドする可能性があります。今からこの領域に取組むということは緊急度が高くなる前に取組むということでもあり、本来の意味でのリスクマネジメントにもつながってきます。 D領域 この領域に取組むことは現実から逃げている可能性があります。そもそも取組む必要性があるかを検討します。
ステップ②:誰のための目標かを検討 『目標って誰のためのモノなのか?』を検討します。もちろん“自分のためのモノ”ですが、組織目標とあまりにも乖離している場合は問題です。そのことを念頭に置いて頂き次の視点で検討を行ないます。 ・目標を達成することで自分自身にとってどういったメリットがあるのか? ・目標を達成することは自分自身にとってどんな意味があるのか? ・目標を達成することで組織(法人・施設・部門)にどのような貢献ができるのか? ・目標を達成したら組織(法人・施設・部門)にとってどんな成果があがるのか? 個人の意見も尊重しながら、組織として目指す方向にベクトルを合わせることがポイントとなります。
ステップ③:具体的になっているかを検討 目標が具体的になっていないと、なかなか行動に移すことはできません。特に『~を図る』・『~を迅速化する』・『~を効率化する』という抽象的な表現には注意が必要です。この様な場合は『クレーム件数●件を■月までに▲件に減少させる』とか『所要時間●時間の作業を■月までに▲時間にする』といった様に“いつまでにどうする”という具体的な表現に変えることがポイントとなります。
上記でご紹介をさせて頂いた以外にも気をつける視点は多々ありますが、最も重要な3つをご紹介させて頂きました。この3つの視点を持つだけでも、今まで以上に視野が広がり効果的な目標設定になるのではないでしょうか。 少しでも皆さまのお役に立てて頂ければ幸いです。 本年度(24年度)あと2ヶ月も残っています。どのようなことに取組みますか?
株式会社 経営開発センター 福祉経営部 松本 和哉 |